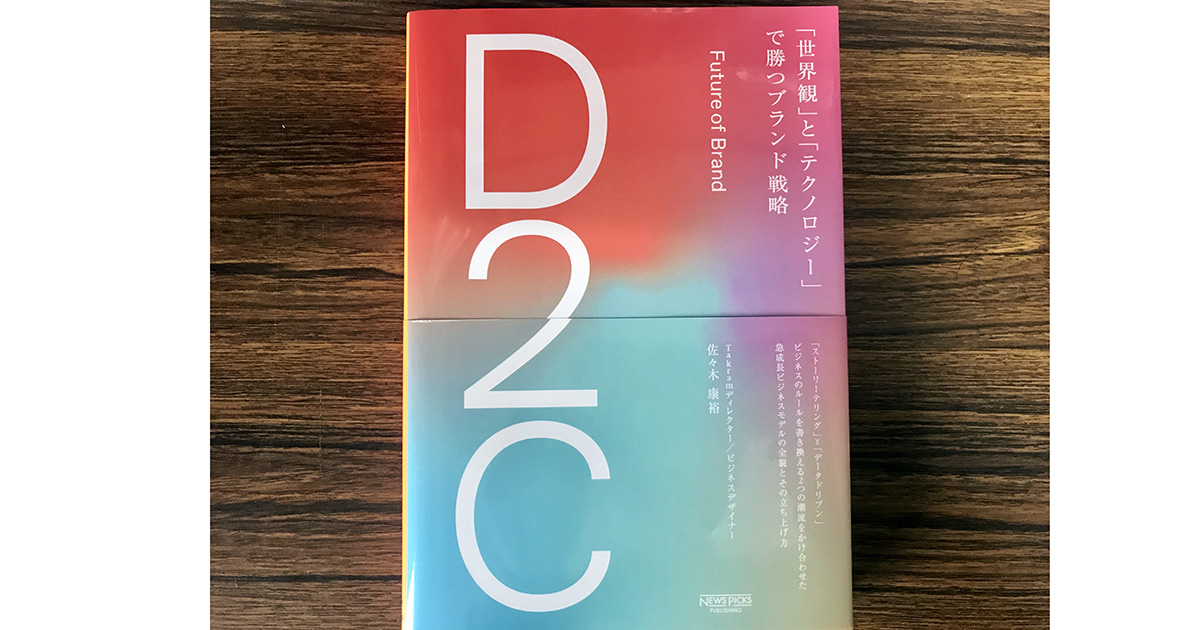問屋・卸に対する一般消費者のネガティブイメージ
日本でも、本格的なチェーンストア企業ができはじめた1960年代頃から「問屋不要論」と呼ばれる考え方が出てきました。
そのざっくりした、内容を解説するならば、
・以前のような中小零細の小売店ばかりの時代ではなく、量販をできる大手のチェーンストア企業が育ってきている。
・メーカーが大手のチェーンストア企業に直接商品を納入するような時代になれば、中間に入る問屋などの卸売業者は不要である。
・むしろ問屋を外した方がマージンを省くことができ、安価に販売できる。これぞ流通革命だ!
というもので、中間マージンを掠め取る問屋こそが、日本の商品が高い原因と、問屋を厳しく糾弾するものでした。
こうした論調は、チェーンストア企業が自身の合理性や正当性をPRするための材料となりえます。
そのため、チェーンストア企業は盛んに「中間マージン」を省いた「直接仕入れ」こそが、値段を安くする唯一の道で、顧客志向なのだ、と徹底的に宣伝をしました。
既存の流通プロセスは何段階もあるのに、このチェーンストアは直接取り引きをしている、というような図を見たことのある方も多いと思います。
こうした熱心な教育?の結果、一般の消費者の方でも、「問屋=中間マージン=悪」「生産者との直接取り引き=中間マージン削減=善」というような印象を持っておられる方も多いと思います。
問屋は本当に悪なのか?
確かに、当時の日本の流通の構造は、卸、二次卸、三次卸というように、大手から零細まで卸売業者が、数珠つなぎになっている構造で、非常に高コスト体質な構造でした。
もっとも、これは昔の会社の事務処理能力には限界があったためです。
多くの顧客企業の注文や在庫を管理するのは、手作業の時代では難しかったのです。
注文書を1通1通郵便で受け取り、1つ1つ手書きで請求書を発行して、宛名を手書きして・・・と、パソコンの無い世界の仕事をイメージいただければ、良く分かると思います。
そのような制約もあったことから、商品ごとや地域ごと、取引先の規模ごとなどに役割を分担していたため、卸売業者の階層構造ができていたのです。
しかし、IT技術の進歩などで、より多くの顧客情報や在庫情報を1つの会社が管理できるようになると、話は違ってきます。
より多くの顧客情報、より多くの商品、より多くの注文データを、驚くほど効率的に捌けるようになっていきます。
たとえば、パソコンに直接、注文が入って、自動的に発注書が完成し、自動的に請求書が作成・印刷され、ラベルまで出てくる・・・というイメージです。
手書きの時代から考えれば、恐るべき事務処理能力の向上です。
そうなれば、より上位の卸業者がより小さな取引先にも商品を納入できる体制が整うことになり、存在意義のなくなる問屋も出てきます。
そういう企業から、真っ先に淘汰が始まり、今ではだいぶ日本の流通もスリム化していると思います。
「やはり問屋を無くすことは、良いことずくめではないか!」と思われるかもしれませんが、こうした話は大手メーカーの規格製品を扱うぶんには良いのです。
「○○社の○○という品番の商品」ということであれば、その商品は、どこで買っても大差はありません。
こうした商品であればメーカー直で取引し、一つでも多くのマージンを省いた方が良いでしょう。
ですが、問屋がなくなっては困る業界もあります。
品質が一定しないような商品を扱う場合です。
「茶」は、その典型とも言える商品だと思います。

産地の茶葉市場
茶問屋は、中抜きできる存在か?
生産者のところで、商品として出荷される「荒茶」は、厳密な意味では規格製品ではありません。
基本的に茶というのは、農産品であり、さらには工芸品のような要素も持ち合わせた商品だからです。
たとえば、同じ茶園・同じ工場で産する製品であっても、「生産した年が違う」「茶摘みの日時が違う」「当日の天候が違う」などの要素によって、生産される茶の品質には微妙な差異が生じます。
同じものは二つと無いのが、本来の「茶」であり、「荒茶」というのはそういう農産品の性質を強く有するものです。
とはいえ、需要家や消費者の方は、そのような農産品感覚では困ってしまうこともあります。
同じ値段の同じメーカーのお茶を買ったのに、ロットや年によって、味の方向性が全然違う・・・ということでは、信頼を得られません。
昨今流行りの”シングルオリジン”という言葉でもって、「それも含めて、お茶の魅力だ」と言い切れれば良いのですが、好事家向けの製品ではなく、一般向けの製品でそれを主張するのは難しいでしょう。
そこで、問屋は荒茶に対して、精製(仕上げ)という工程を施し、品質を安定化させます。
荒茶に含まれる雑味の要素などを取り除いたり、焙煎(火入れ)を行って味を調えたり。
場合によっては、複数のお茶をブレンド(合組)して、安定した味わいのロットに規格化を図るなどして、お茶そのものに付加価値を加えます。
そして、そのプロフェッショナルな仕事の対価として、仕入れた分に適正な利潤を乗せて小売業者に販売をします。
本来の意味の茶問屋は、規格製品を右から左へ流したり、小分けにするだけの事業者ではなく、こうしたプロフェッショナルな事業者なのです。
茶問屋がなかったらどうなるか
仮に茶問屋の存在がなく、生産者と消費者が直接、取引する場合を考えてみましょう。
非常に天候にも恵まれ、品質的に自信のある年ならば、消費者も喜んで買うでしょう。
問屋の分のマージンも乗っていないので、買う方は安いと感じるかもしれませんし、生産者の側も卸売価格より高い小売価格で売れるので、満足かもしれません。
しかし、天候などの理由で品質が仮に悪かった場合、この取引は成立しないことを覚悟しなければなりません。
品質が悪いと感じるものを無条件で買うことなど、消費者は約束しないからです。
もし売れなければ、資金の流れが止まってしまうので、やむを得ず、安売りをすることになるかもしれません。
そうなれば、翌年以降、その値段より高く売ることは困難になります。
直接取り引きの怖さはこうしたところにあります。
しかし、茶問屋というプロフェッショナルを介していれば、とりあえずお茶を引き受けてもらうことはできるでしょう。
そして、彼らの手で茶の欠点を補うような仕上げやブレンドなどを行ってもらうことで、いつも通りの美味しいお茶として、消費者に飲んでもらうことができます。
このような機能を考えると、本来の意味でのプロフェッショナルな、お茶の問屋・卸売業者というのは、茶業界の流通インフラとして欠かせない存在なのです。
輸入茶こそ、プロフェッショナルな卸売業者が必要
さらに言うならば、中国茶・台湾茶などの輸入茶こそ、本来の意味でのプロフェッショナルな卸売業者が必要だと考えています。
その理由としては、まず、現地で販売されているお茶は、玉石混淆であることが多く、それらを見極める確かな鑑定眼が必要であることです。
日本の市場でも散見されますが、「珍しいから」「著名だから」という理由だけで仕入れてきたものの、製茶の工程に明らかな問題を感じるお茶が流通している場合もあります。
そういうお茶は、本来の名茶としての品質に全く届いておらず、しかし値段が不当に安かったりして、その名茶のイメージを毀損するだけになってしまいます。
このような商品を流通させることは、全く業界のためになりません。
これらを弾くためには、そのお茶と製茶プロセスへの理解とそれをきちんと主張できるだけの現地の言葉でのコミュニケーション能力が必要です。
特に中国では全ての産地・製法に通じることは、ほぼ不可能ですので、それぞれの得意分野で豊富な経験を持ったプロフェッショナルが多数必要ではないかと思います。
さらに、輸入食品特有の問題として、食品としての輸入を行う上で必要な、通関手続き(とりわけ残留農薬検査など)を適切かつ効率的に行う必要があることです。
通関の実務については、極端な話、5kgでも1トンでも同じような手間・費用がかかりますし、農薬検査なども必要となる検体の量やコストは、量が少なくても多くてもあまり変わりはありません。
ある程度のスケールメリットを効かせられるのが、この通関の分野です。
各店舗ごとに小口の輸入をするよりは、まとめて一括で輸入を行った方が、輸入コストはより低くなり、結果的に茶の内外価格差を縮めることになるのではないかと思います。
日本における旧来型の中国茶卸は、中華料理店などへの食材の1つとして茶を輸入するという感覚からなのか、価格が優先される傾向が強く、品質的に嗜好品のレベルには達していないものも多くあります。
昨今は、品質の高いお茶を現地で味わった経験のある日本人も増えてきていますので、それとは一線を画した高品質な茶を輸入する、プロフェッショナルな卸売業者も活躍の場は広がってきているのではないかと思います。
次回は3月12日の更新を予定しています。